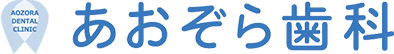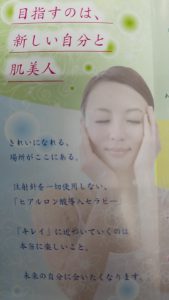ブログ
口内炎はどうしてできるのでしょうか?
CT完備井高野井高野あおぞら歯科北江口口内炎口腔外科口腔粘膜吹田市土日診療定期検診摂津市東淀川区歯科検診無痛治療舌がん舌が痛い頬が痛い駐車場完備
口内炎でお食事をする際、痛みがあり食べることが困難だったり、食事の量を減らしたり
苦労されていることをよく耳にします。
口内炎とはお口の中やその周辺の粘膜に起こる炎症の総称をいいます。
主に頬粘膜や舌などにできやすく、広範囲に発生するもので、多くが痛みを生じます。
その中で多いものがアフタ性口内炎といわれるものがあります。
白色か黄色の膜で覆われた約1㎜から約10㎜くらいの潰瘍ができて、食事の時にしみる痛さが
あります。ほとんどの場合1~2週間くらいで治ってきますが、繰り返してできてくることが多いのです。
このことを再発性アフタといいます。
口内炎ができる要因は様々なことがあります。
①栄養バランスの乱れによるもの
偏りのある食生活で口内炎ができることがあります。
どの栄養素が原因で口内炎ができやすいと断定できるのは不明ですが、一部ではビタミンBが関係していると
いわれています。
健康のためにもバランスの良い食事を心がけましょう。
②口腔内の細菌やウイルスによるもの
口腔内の細菌にはいろんな種類のものが存在します。
口腔内の常在細菌のバランスが崩れることにより、口腔内の環境が悪化して口腔粘膜や舌や歯ぐきに
潰瘍性の口内炎ができることがあります。
③機械的な刺激によるもの
歯がとがっていたり、頬粘膜や舌を噛んでしまったり、入れ歯の形態によって傷ができたり、
詰め物やかぶせ物の刺激により(金属アレルギーなど)口内炎ができることもあります。
④免疫の低下によるもの
睡眠不足やストレスを溜めることなどによって免疫力が低下してしまい、口内炎ができやすくなります。
免疫力が低下すると粘膜の再生力も低下し粘膜が潰瘍を作りやすくなったり、荒れたりして口内炎ができやすく
なります。
⑤病気や薬によるもの
口内炎が繰り返してできたり、長期化する場合は病気の可能性があります。
2週間経過しても治らなかったり、1㎝以上の大きさの口内炎ができやすいならば、
一度歯科医院で口腔粘膜疾患があるか調べてもらいましょう。
当医院では口腔粘膜疾患診断カメラがありますので、調べることが可能です。
⑥口腔内の乾燥によるもの
唾液の働きにより、抗菌作用やお口を潤わす作用や口腔粘膜を保護する作用があります。
加齢やお薬の副作用により唾液の分泌量が減っていくことによって粘膜に細菌が侵入することで
口内炎ができやすくなります。
口内炎で悩んだり、痛いときには歯科医院で薬液やレーザー治療などで痛みの軽減を
してみましょう。
井高野あおぞら歯科
大阪市東淀川区井高野3-2-40
06-6827-1919
おすすめ記事
月別アーカイブ
- 2024年7月
- 2024年6月
- 2024年5月
- 2024年4月
- 2024年3月
- 2024年2月
- 2024年1月
- 2023年12月
- 2023年11月
- 2023年10月
- 2023年9月
- 2023年8月
- 2023年7月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2023年3月
- 2023年2月
- 2023年1月
- 2022年12月
- 2022年11月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年6月
- 2022年5月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2022年2月
- 2022年1月
- 2021年12月
- 2021年11月
- 2021年10月
- 2021年9月
- 2021年8月
- 2021年7月
- 2021年6月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年3月
- 2021年2月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年11月
- 2020年10月
- 2020年9月
- 2020年8月
- 2020年7月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2020年2月
- 2020年1月
- 2019年12月
- 2019年11月
- 2019年10月
- 2019年9月
- 2019年8月
- 2019年7月
- 2019年6月
- 2019年5月
- 2019年4月
- 2019年3月
- 2019年1月
- 2018年12月
- 2018年11月
最近の記事

お知らせ
8月の休診日について

ブログ
口臭が気になっていませんか?
CT完備あおぞら歯科あおぞら歯科井高野上新庄井高野井高野あおぞら歯科北江口南江口口臭口臭予防口臭外来口臭治療口臭防止吹田市土日診療大阪市大阪市東淀川区摂津市東淀川区駐車場完備

お知らせ
7月の休診日について